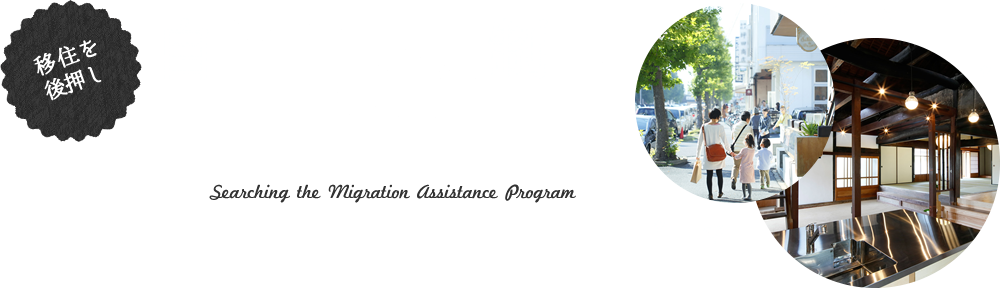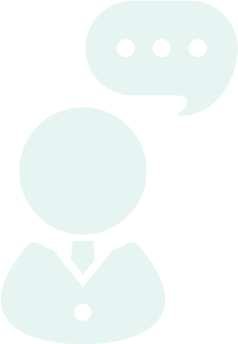1. はじめに|「農業を始めたい」と思ったあなたへ

「いつか自然の中で暮らしたい」「自分で作った野菜を育てて暮らしたい」「食に関わる仕事がしたい」――そんな思いから、農業を始めたいと考える方が増えています。実際に、近年は20〜30代の若手から、定年後のセカンドキャリアとして農業に挑戦する人まで、新たに農業の道へ踏み出す“新規就農者”が全国的に増加中です。
背景には、地方移住やスローライフへの関心の高まりに加え、国や自治体による就農支援制度の充実もあります。未経験でも技術を学べる研修制度や、資金を支援する補助金など、ゼロからでもスタートしやすい環境が少しずつ整ってきているのです。
とはいえ、農業は自然を相手にする仕事であり、簡単に儲かるものではありません。体力も必要ですし、準備することや乗り越えるべき壁もたくさんあります。だからこそ、「農業を始めるには何が必要か」を正しく知っておくことが、成功への第一歩になります。
この記事では、農業を仕事として始める際に必要な準備や手続き、就農までのステップ、活用できる支援制度などをわかりやすく解説していきます。「いつかやりたい」を「今から準備できる」に変えるためのヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。
2. 農業を始める前に考えるべき3つのポイント

「農業をやってみたい!」という気持ちはとても大切ですが、勢いだけで始めてしまうと、思っていた以上のハードさや現実とのギャップに直面することがあります。だからこそ、就農前にしっかりと考えておくべき3つの視点があります。
① なぜ農業をやりたいのか?(目的・ビジョンの明確化)
まず最初に、自分がなぜ農業を始めたいのか、どんな暮らしや働き方を望んでいるのかを明確にしておくことが重要です。
たとえば、
- 地方でのんびりとした生活を送りたいのか
- 独立して自分のビジネスを持ちたいのか
- 自然と触れ合いながら家族で暮らしたいのか
目的によって「選ぶ作物」「働き方」「収入の目標」などが変わってきます。夢や理想を言語化し、それを実現するための就農プランを描くことが第一歩です。
② どんな作物を、どこで育てたいのか?(環境・地域・気候)
農業は土地や気候に強く影響されます。「どこで何を作るか」は、経営にも生活にも大きな影響を与えます。
たとえば、
- 米作りなら水資源の豊富な地域や大規模な土地が必要
- 高収益を狙うなら果樹や施設野菜の選択肢も
- 地域ブランドや販路(直売所・観光客向け)を生かせる立地かどうか
このように、自分が目指すスタイルと地域性との相性を見極めることが、継続的に農業を続けるうえで重要になります。
③ 農業を“仕事”として続けられるか?(収入・生活設計)
農業は“自然と共に暮らす仕事”であると同時に、“生活の糧を得るビジネス”でもあります。特に新規就農者にとっては、収入が安定するまでに時間がかかる場合もあり、生活設計をしっかり立てておくことが欠かせません。
- 初年度の収入はどれくらい見込めるのか
- 家族がいる場合、生活費・教育費はどう賄うのか
- 収入が少ない間をどう乗り切るか(貯金・副業・支援制度など)
このように、農業を「好き」だけで始めるのではなく、「続けられるか」の視点を持っておくことが、後悔しない就農につながります。
この3つのポイントを出発点として、自分に合った就農スタイルや地域選び、準備の進め方を考えていきましょう。次章では、実際にどんな就農の形があるのかを紹介していきます。
3. 新規就農の主なスタイル4つ

新規就農と一口に言っても、その始め方は人によってさまざまです。ここでは、未経験者でも選べる4つの主なスタイルを紹介します。自身の目的やライフプランに合った方法を見つけることが、成功への第一歩です。
3-1. 独立就農(農地・機材を自分で揃えて始める)
自由度が高く、自分の理想の農業に挑戦できるスタイル。
農地を自ら借りて設備を整え、個人事業主または法人として事業を立ち上げます。
メリット:
・作物や経営スタイルを自由に決められる
・成功すれば収入・やりがいともに大きい
・国や自治体の補助金対象になりやすい
デメリット:
・初期投資・知識・リスク管理が必要
・農地探しや地域との関係づくりが大変
向いている人:
農業を事業として自立して行いたい人、自分で工夫しながら挑戦したい人
3-2. 雇用就農(農業法人などに就職して働く)
農業法人などに就職し、給料を得ながら農業に関わるスタイル。
初心者が基礎から実務を学ぶ手段として人気です。
メリット:
・安定した収入が得られ、生活基盤が確保しやすい
・経験を積みながら、農業経営の現場を学べる
デメリット:
・作物や作業内容は会社の方針に依存
・独立を目指す場合は別途準備が必要
向いている人:
いきなり独立は不安な人、まず現場で農業のリアルを学びたい人
3-3. 親元就農(家族の農業を継ぐ/実家の農地を活かす)
家業としての農業を継承するスタイル。
農地・設備・ノウハウが身近にあり、スタートしやすいのが特長です。
メリット:
・初期費用を抑えられる
・経験豊富な親から直接学べる
・地域とのつながりが既にある
デメリット:
・経営権や方針で親との対立が起こることも
・「古いやり方」に縛られがち
向いている人:
実家が農家で、将来的に継ぐ予定の人/地元に戻って働きたい人
3-4. 農業承継(他人の農業経営を引き継ぐ)
高齢農家や後継者のいない農家から、農地・設備・ノウハウを“事業として引き継ぐ”スタイル。
農業版M&Aとも呼ばれ、後継者不足の課題を解決しつつ、新規参入者にもメリットのある方法です。
メリット:
・農地や機械がすでに整っているため、初期投資を抑えられる
・顧客・販路・栽培ノウハウを引き継げる
・地域からの信頼も得やすい
デメリット:
・経営状況や土地条件をよく確認する必要あり
・農家との相性や信頼関係の構築がカギ
向いている人:
事業として農業を始めたいがゼロからの立ち上げに不安がある人/地域で長く続けたい人

農業の始め方は一つではありません。自分の性格や資金状況、ライフプランに合わせて、「どのスタイルが最も現実的か、続けやすいか」をじっくり見極めることが、新規就農を成功させる大きなカギになります。
4. 農業を始めるために必要な準備・手続き

「農業をやってみたい」という気持ちを行動に移すには、しっかりとした準備が不可欠です。農地や住まい、資金、技術など、考えるべきことは多岐にわたりますが、ひとつずつ着実に進めていくことで、就農の実現がグッと近づきます。ここでは、農業を本格的に始めるために必要な代表的な準備項目を4つご紹介します。
4-1. 農地の確保|最初に向き合う“壁”
農業を始めるうえで真っ先に必要になるのが、作物を育てるための農地です。ただし、日本では農地法によって取引が厳しく制限されており、誰でも自由に買ったり借りたりできるわけではありません。農地を取得・借用する際は、農業委員会の許可が必要で、農業に継続して取り組む意思や具体的な計画が求められます。
最近では、農地を探している人と貸したい農家をつなぐ「農地中間管理機構」などの仕組みもあり、新規就農者を歓迎する地域では比較的スムーズに農地を借りられるケースも増えています。早い段階で自治体やJA、農業委員会に相談し、信頼関係を築いておくことが大切です。
重要ポイント:
・農地の取得・貸借には農業委員会の許可が必要
・地域や条件によって取得の難易度が異なる
4-2. 住居と暮らしの設計|“どこで、どう暮らすか”を考える
農地が決まれば、次に必要なのが生活拠点です。特に都市部から移住を伴う場合は、住まいや生活環境の変化に対する備えが欠かせません。空き家を利用できる自治体や、移住者向けの住宅補助を行っている地域もあるので、地域選びは就農計画と並行して進めることが理想です。
また、子育てや医療、買い物環境など、暮らし全体の利便性を事前に把握しておくことで、就農後のストレスを減らすことができます。可能であれば短期滞在や体験就農などを通じて、その地域で実際に過ごしてみると安心です。
重要ポイント:
・移住支援や空き家バンクを活用できる地域も多い
・地域に根ざした暮らしを前提に、生活設計を立てる
4-3. 資金の準備|“思ったよりお金がかかる”現実
農業は、土地があればすぐに始められるというものではありません。農機具や資材、設備、肥料など初期費用がかかり、さらに収穫までの数ヶ月〜1年は収入が得られないため、その間の生活資金も確保しておく必要があります。
こうした費用に対しては、貯金だけでなく融資や補助金の活用が現実的です。国の制度として「農業次世代人材投資資金」や、日本政策金融公庫による就農者向け融資、自治体の支援金制度なども充実してきています。
重要ポイント:
・初期費用だけでなく、収穫までの生活費も見込んで準備
・融資や補助金制度を活用して資金負担を軽減
4-4. 栽培技術と知識の習得|“作れる”と“売れる”は違う
農業における成功は、作物をうまく育てるだけではありません。**安定した品質と収量を保ち、きちんと販路を確保して利益を出す“経営”の視点も必要です。**そのためには、就農前の段階で栽培の基本だけでなく、経営や販売に関する知識も身につけておくとよいでしょう。
農業大学校や各地の就農準備校では、1年〜2年程度の研修制度を通じて、現場での実践とともに知識や技術を学ぶことができます。また、先輩農家のもとで働きながら学ぶ「トライアル就農」などの制度も、新規参入者にとっては有効な手段です。
重要ポイント:
・研修制度や農業学校を通じて、技術と経営感覚を身につける
・現場で学ぶ経験が、独立後の安定経営につながる
5. 新規就農のステップ【6ステップで解説】

農業を始めたいと思っても、「何から手をつければいいのかわからない」という方は多いでしょう。新規就農には段階を踏んだ準備が必要ですが、逆に言えば、一歩ずつ進めていけば誰でも現実にできる道でもあります。ここでは、就農までのプロセスを6つのステップに分けて、わかりやすく解説します。
最初に必要なのは、「なぜ農業をやりたいのか」をはっきりさせることです。自然の中で暮らしたい、食の安全に貢献したい、地域に根ざして働きたいなど、理由は人それぞれ。
ですが、この動機があいまいなままだと、準備や実践の段階で迷いが生じやすくなります。就農後の生活や将来像まで含めて、自分がどんな農業をしたいのかを言語化することが大切です。
次に考えるべきは、「どこで」「何を育てるか」という点です。地域によって気候・土壌・販路・支援制度が異なり、作物の適性も変わってきます。また、作物ごとに必要な設備や労力も違うため、収益性や作業量をよく調べたうえで選ぶことが重要です。
気になる地域には実際に足を運び、自治体やJAの担当者、現地の農家に話を聞くことで、よりリアルな情報を得られます。
思い描く農業と、実際の現場にはギャップがあるものです。そこで重要なのが、農業体験やインターンへの参加です。短期でも現地の空気を感じ、作業内容や生活環境を体験することで、向き・不向きの判断材料になります。
自治体や就農支援センターでは、「トライアル就農」「農業体験ツアー」などのプログラムを用意している場合も多く、就農前に複数の地域を比較検討するのも有効です。
農業は現場での経験がすべてとも言われます。そこで、就農準備校や農業大学校、民間研修先での実践研修を通じて、1〜2年間かけて技術と経営を学ぶのが一般的です。
研修では、土作りや苗管理、収穫などの基本作業はもちろん、販売や経営管理といった“稼ぐ力”も養うことができます。「作る」と「売る」の両方を学べる環境に身を置くことが、就農後の安定経営につながります。
知識とスキルを身につけたら、次は就農に向けた基盤の整備です。農地の確保には農業委員会の許可が必要で、計画性や地域との信頼関係も重要となります。また、機械・資材・住宅などの初期投資には多くの費用がかかるため、補助金や融資制度を活用しながら資金計画を立てましょう。
この段階で、「営農計画書」や「収支見込み」などの書類づくりも必要になってくるため、就農相談窓口などで専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
いよいよ就農スタート。とはいえ、作って終わりではなく、「どう売るか」「どう続けるか」が本当の勝負です。 直売所、道の駅、ネット通販、ふるさと納税、飲食店との契約栽培など、作物に応じた販路開拓を行い、安定した売上につなげていきましょう。
地域内での信頼や口コミも重要になるため、日々の誠実な対応や積極的な情報発信も収益に直結します。 少しずつ実績を積み上げて、地に足のついた農業経営を目指しましょう。
ここまでご紹介した6つのステップは、新規就農の王道ルートといえます。しかし実は、もうひとつ効率的なスタート方法として注目されているのが「農業承継」という選択肢です。
農業承継とは、すでに農業を営んでいる高齢農家などから農地・設備・販路・技術などを引き継いで農業を始める方法です。現在、多くの地域で後継者不足が深刻化しており、熱意ある新規就農者に継がれることを望んでいる農家が多数存在します。
一般的な新規就農では、
- 農地を探すだけで時間がかかる
- 設備投資や販路開拓をゼロから始める必要がある
- そもそも「何を作れば売れるか」が分からない
といった課題が山積しています。一方で農業承継は、すでに確立された経営資源を受け継ぐことができるため、非常に効率的かつ実践的に農業を始めることができる手段として注目されています。
地域によっては農業承継に特化したマッチング支援制度もあり、「後継者になってくれるなら、農地も設備も無償で譲渡します」というケースも珍しくありません。
「本気で農業を仕事にしたい」「時間を無駄にせず確実にスタートを切りたい」という方にとっては、農業承継は非常に現実的で価値のある道です。
農業承継の詳細はこちら

このように、王道ルートで1から準備を進める方法に加えて、すでにある農業経営を“引き継ぐ”というルートもあることを知っておくだけで、あなたの選択肢はぐんと広がります。
自分に合ったスタイルで、着実に一歩を踏み出してみてください。
6. 就農をサポートしてくれる主な制度・支援一覧
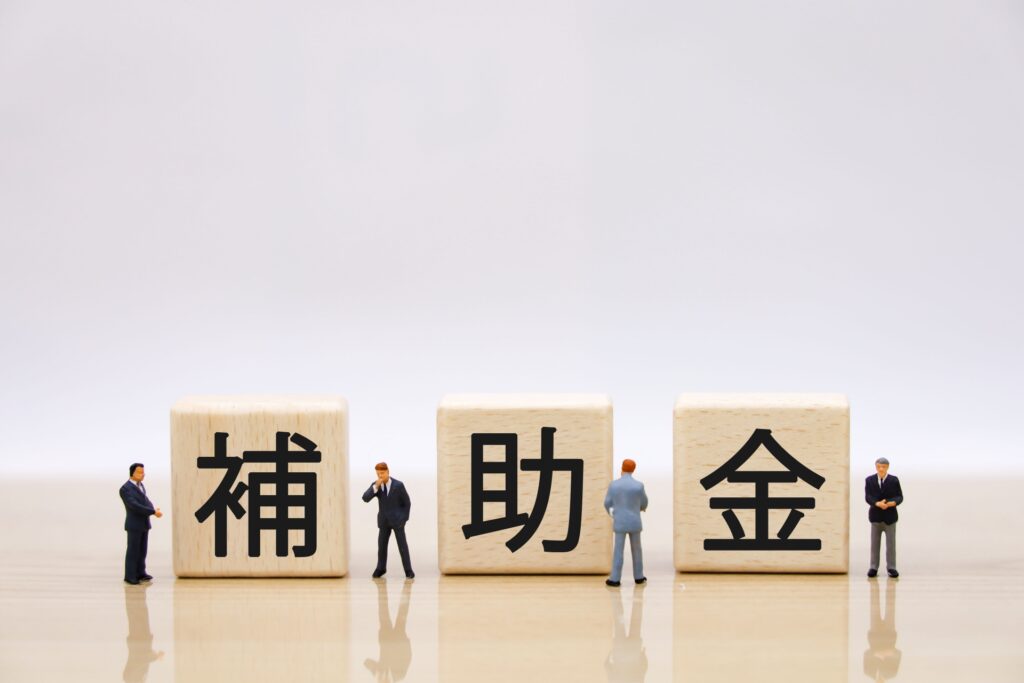
新しく農業を始めるには、農地や設備、生活費など、さまざまな負担が伴います。ですが、国や自治体ではこうしたハードルを乗り越えるために、新規就農者向けの支援制度が多数用意されています。
ここでは、特に活用されやすい主要な制度をご紹介します。
6-1. 農業次世代人材投資資金(旧:青年就農給付金)
新規就農希望者にもっとも広く知られている支援制度の一つです。
この制度は、就農に向けて研修を受ける「準備型」と、独立・自営就農後の「経営開始型」の2種類があります。
- 準備型:年間最大150万円(最長2年間)を給付
- 経営開始型:年間最大150万円(最長5年間)を給付
※ともに条件あり。自治体や地域の認定を受ける必要があります。
生活費や農業学校への通学費をカバーできるため、資金面での不安が大きく軽減されます。
6-2. 農地中間管理機構(農地マッチング制度)
農地を借りたい人と、貸したい農家をつなぐ国主導の農地マッチング制度です。都道府県ごとに機構が設置されており、農地をスムーズに確保したい新規就農者にとっては非常に心強い存在です。
- 農業委員会と連携して農地探しをサポート
- 借り手の信用性を担保するため、地域との橋渡しも行う
農地法の制限をクリアするためにも、初めて農地に関わる人はこの制度の活用を前提に動くのがおすすめです。
6-3. 各自治体の移住支援・就農支援制度
多くの地方自治体では、若者や移住者の就農を促進するための独自の制度を設けています。
地域によって支援内容は異なりますが、以下のようなサポートが用意されているケースが多くあります。
- 就農支援金や家賃補助、住宅改修費の助成
- 農業体験ツアーや地域とのマッチングイベント
- 農機・ハウス導入の補助金制度
まずは興味のある地域の役場(農政課など)や地域おこし協力隊担当窓口に相談してみると、具体的な支援内容がわかります。

6-4. 農業委員会・JAのサポート
農業を始めるうえで欠かせない存在が、地域の農業委員会やJA(農協)です。
農地の手続きや許可申請、技術相談、資材の手配、出荷先の紹介など、地元に根差した実務的なサポートを受けることができます。
特に農業委員会は、農地の賃貸借に関する法的な審査・承認を行う重要な組織です。
就農をスムーズに進めるためには、早い段階で地域の担当者と信頼関係を築くことがポイントになります。
6-5. 制度を活用するためのポイント
各制度は非常に有用ですが、申請には事前準備や条件があることがほとんどです。
たとえば、「農業経営改善計画(営農計画書)」の提出や、地域の認定制度への登録などが求められます。
制度を受けることが目的になってしまわないように、あくまで“就農の実現と継続のための手段”として位置づけることが大切です。
わからないことがあれば、地域の就農相談窓口や農業普及センターに相談することで、的確なアドバイスを受けることができます。
7. まとめ|夢だけでなく、現実と向き合う“覚悟”が成功のカギ
農業を始めるという選択は、都会の喧騒から離れ、自然とともに生きる魅力的なライフスタイルである一方、決して楽な道ではありません。天候や自然災害に左右される不安定さ、収入が軌道に乗るまでの時間、慣れない土地での人間関係――新規就農には、乗り越えるべき壁がいくつもあります。
けれど、その現実をしっかり見据えたうえで準備を進め、周囲の支援や制度を活用しながら、自分のスタイルで就農を実現している人も確かに存在します。
大切なのは、「夢」だけで突き進むのではなく、「現実」と丁寧に向き合いながら前に進む姿勢です。目的を明確にし、段階的に準備を重ね、必要なときは支援を受けながら、自分らしい農業の形を見つけていくことが、長く続けていくための秘訣です。
農業は、“暮らし”と“仕事”が一体になる仕事。日々の積み重ねが、土地に根を張るように少しずつ形になっていきます。
「農業を始めたい」と思った今が、人生の転機になるかもしれません。
小さな一歩でも、確かな一歩を。あなたの就農の道が、実りある未来へとつながっていくことを願っています。