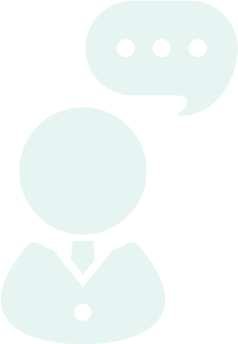1. はじめに|「農業を始めたいけど、費用が不安」という方へ

「農業を始めてみたい」「自然の中で働く暮らしに憧れる」
そう思っている方が増えている一方で、なかなか最初の一歩を踏み出せない理由としてもっとも多いのが、“お金の問題”です。
実際、農業を始めるには農地や設備、資材の準備だけでなく、作物が育ち収穫・販売できるようになるまでの生活費や運転資金も確保しておく必要があります。
「一体いくらかかるの?」「貯金が少なくても始められるの?」「補助金は使えるの?」といった不安を感じるのは、ごく自然なことです。
ですが、心配はいりません。
近年では、新規就農者を支援するための制度や補助金・助成金が整備されており、工夫と準備をすれば、資金面のハードルは乗り越えることができます。
さらに、「農業承継」という方法を活用すれば、ゼロから始めるよりも大幅にコストを抑えて就農することも可能です。
この記事では、新規就農にかかる費用の内訳や相場感、利用できる主な支援制度、そしてコストを抑えて始めるための実践的な方法まで、わかりやすく解説します。
「費用面の不安を解消して、農業を始めるための現実的な準備をしたい」
そんなあなたのための一歩として、ぜひ最後までご覧ください。
2. 新規就農にかかる費用の内訳

新規就農を目指すにあたって、まず把握しておきたいのが「実際にどれくらいの費用がかかるのか」ということ。
就農にはさまざまな準備が必要で、農地や機材などの“見えるコスト”だけでなく、生活費や運転資金といった“見えにくいコスト”も含めて考えておくことが重要です。
ここでは、主な費用項目とその目安について、カテゴリごとに解説していきます。
① 農地の確保・整備費(数十万円〜)
農地を借りる、もしくは購入する場合には、それにかかる初期費用が発生します。
日本では農地法により、農地の貸借には農業委員会の許可が必要です。地域によっては、農地中間管理機構を通じて借りやすくなっており、初期費用を抑えたスタートも可能です。
ただし、長年使われていなかった農地の場合は、草刈り・土壌改良・水路整備などの圃場整備費が別途必要になることもあります。
② 設備投資費(数十万〜数百万円)
農業を始めるには、必要な作業機械や資材、施設を整えるための初期投資が必要です。
- ビニールハウスの建設(1棟あたり100〜300万円)
- トラクターや管理機などの農機具(中古でも20〜200万円)
- 潅水設備・倉庫・冷蔵庫などの付帯設備
作物の種類や生産規模によって必要な設備は大きく異なりますが、一気にすべてを揃えようとせず、必要最低限から始める“スモールスタート”が現実的です。
③ 資材・種苗費(年間数万円〜)
作物を育てるには、苗・種子・肥料・農薬・資材(マルチ・支柱など)といった消耗品が必要です。
これらは毎年発生する“ランニングコスト”でもあるため、就農前にざっくりと年間コストを試算しておくことが大切です。
例:
・トマト:約20〜30万円/10a
・米:約15万円/1反(10a)
④ 住居・移住費用(0〜数百万円)
地方に移住して就農する場合は、住居費用や引っ越し費用も計算に入れておきましょう。
地域によっては空き家バンクの活用や、移住者向けの住宅補助制度などが用意されていることもあります。
また、リフォームや修繕が必要な住居の場合は、数十万円〜数百万円の費用が発生することもあるため、事前に確認しておくのがベターです。
⑤ 生活費・運転資金(6ヶ月〜1年分)
新規就農1年目は、すぐに収穫や売上につながらない期間が続くことが多いため、その間の生活費や事業の運転資金も確保しておく必要があります。
- 家族がいる場合:生活費+教育・医療・保険などの支出も想定
- 単身者の場合:最低でも年間100〜150万円は見込んでおくと安心
💡 合計でどれくらいかかる?
就農形態や作物にもよりますが、新規就農には概ね200万円〜1,000万円程度の初期費用がかかるといわれています。
ただし、すべてを自己資金で用意する必要はありません。
次章では、この費用をどのように補助金・助成金・融資制度でカバーできるのかを詳しく解説していきます。
3. 自己資金だけじゃない!利用できる主な補助金・助成金制度

新規就農には数百万円単位の費用がかかる場合もあり、「そんなお金、準備できない…」と感じる方も多いかもしれません。
しかし近年では、国や自治体による補助金・助成金・融資制度が充実しており、資金面の負担を大きく軽減することが可能です。
この章では、代表的な支援制度とその活用方法について解説します。
3-1. 農業次世代人材投資資金(準備型・経営開始型)
新規就農希望者にとって、最も利用されている制度のひとつがこの「農業次世代人材投資資金」です。
農林水産省が管轄しており、研修中の生活費や、就農初期の経営安定をサポートするために支給される給付金です。
【準備型】
・対象:農業大学校や地域の研修機関などで研修を受ける方
・金額:年間最大150万円(最長2年間)
・特徴:無返済(条件あり)
【経営開始型】
・対象:独立・自営就農した方(認定新規就農者)
・金額:年間最大150万円(最長5年間)
・特徴:経営改善の取り組みが前提条件
🔍 ポイント:
事前に「青年等就農計画」や「就農開始日」の認定申請が必要。早めに自治体や農業委員会に相談しましょう。
3-2. 就農支援資金(日本政策金融公庫)
「農業を始めるための設備投資や運転資金が足りない」という方に向けて、日本政策金融公庫が提供する無利子融資制度もあります。
- 融資限度額:最大3,700万円(うち運転資金は最大1,200万円)
- 利率:実質無利子(条件を満たした場合)
- 据置期間:最大5年/返済期間:最長12年
この融資は、補助金と組み合わせて使うことも可能であり、「自己資金は少ないけれど、就農の意欲と計画はある」という人にとっては非常に強力なサポートです。
3-3. 各自治体の就農・移住支援制度
地方自治体では、移住促進や担い手育成のために独自の就農支援金・家賃補助・住宅改修費助成などを用意していることがあります。
例)
・移住支援金(最大100万円)
・空き家バンクの利用+リフォーム補助金
・地域独自の新規就農奨励金(年20〜50万円など)
・地域おこし協力隊の活動費(年240万円程度)
🔍 ポイント:
制度内容は地域によって大きく異なるため、「この地域で就農したい」と思ったら早めに市町村の農政課やJAに相談することが重要です。

3-4. 補助金申請で準備しておきたいこと
支援制度を活用するためには、以下のような準備が必要になります。
- 就農計画書(営農・収支計画)
- 希望作物の選定理由や販売戦略
- 研修計画や就農地の目処(ある場合)
- 必要資金と自己資金の内訳
これらの資料は、補助金だけでなく融資や農業承継の際にも必要となるため、早い段階で作り始めておくと、スムーズに次のアクションが取れます。
💡 自己資金ゼロでも本当に始められる?
支援制度や融資を上手に活用すれば、自己資金がほとんどなくても新規就農を実現することは可能です。
特に、「農業承継」を活用する場合は、農地・設備・販路などがすでに揃った状態から始められるため、費用負担が大幅に軽減されるという大きなメリットがあります。
次章では、その「農業承継」という選択肢について詳しくご紹介していきます。
4. 「農業承継」なら費用を大幅に抑えられる?

ここまで、農業をゼロから始める場合に必要な資金や補助制度をご紹介してきましたが、実はもうひとつ注目すべき就農ルートがあります。
それが、「農業承継」――すでに農業を営んでいる人から経営を引き継ぐという方法です。
農業というと、自分で農地を探し、設備を整え、作物を選んで販路を開拓する――という「ゼロからのスタート」が一般的に思われがちですが、農業承継はその常識を大きく覆します。
4-1. なぜ、農業承継は費用を抑えられるのか?
農業承継では、次のような「すでにある資産・仕組み」を活用することができます。
- 農地(使用権や契約がそのまま移行できることも)
- トラクターや農機具、ビニールハウスなどの設備一式
- 出荷先や販売先などの販路
- 地域内での信頼関係やネットワーク
- 栽培ノウハウや年間スケジュール、帳簿などの経営資料
つまり、これらを“買う・作る・探す”必要がなくなることで、時間的にも金銭的にも大幅なコスト削減が可能になるのです。
また、後継者を探している農家の中には、「若い人に託せるなら設備は無償で譲る」というケースも少なくありません。これが、農業承継の強みです。
4-2. ゼロスタートでは得られない“信頼”と“環境”
新規就農者が最初にぶつかる壁のひとつが、「地域との関係づくり」です。
農業は土地・人・季節と深く関わる仕事であるため、地域の理解や協力が得られるかどうかが、その後の継続に大きく影響します。
農業承継の場合は、すでに地域に根付いている農業経営を引き継ぐことで、その信頼関係や人間関係も一緒に引き継げる可能性があり、スムーズな立ち上がりにつながります。
4-3. FARMLINKでできること
- 全国の承継希望農家の情報を検索・相談できる
- 農地・設備の有無や譲渡条件が明確だから比較検討しやすい
- 個人間では難しい契約面や条件交渉も、サポートを受けながら安心して進められる
- 第三者承継(親族以外への承継)にも特化しており、農家出身でなくても利用可能
FARMLINKを活用すれば、「就農したいけれど土地もツテもない…」という人でも、現実的かつスピーディに農業を始めることができます。

4-4. 自分に合ったスタートを選ぼう
農業承継は、あくまで「農業の始め方のひとつ」ですが、資金面・時間面・地域との関係性において、非常に合理的で再現性の高い方法です。
ゼロからの挑戦も魅力的ですが、「既存の農業経営をベースに、自分らしい農業を育てていく」――そんなスタイルにも、大きな可能性が広がっています。
次章では、就農までの資金調達や補助金申請をスムーズに進めるための準備と流れについて解説していきます。
5. 資金調達の流れと事前準備のポイント

新規就農を実現するためには、「農地や設備の確保」だけでなく、それらにかかる費用をどう用意するか――つまり資金調達の戦略も非常に重要です。
自己資金に頼り切るのではなく、補助金・助成金・融資制度を上手に組み合わせていくことで、無理のないスタートが可能になります。
ここでは、実際の資金調達の流れと、事前に準備しておくべきポイントを紹介します。
まず最初に必要なのが、「どこで」「何を」「どのくらいの規模で」始めるのかという全体像の明確化です。
これが定まっていないと、必要な資金の見積もりも不明確になり、補助金の申請や融資交渉の説得力も薄れてしまいます。
考えるべき主なポイント:
- 作物の種類と栽培面積
- 設備投資の内容(機械、ハウス、倉庫など)
- 農地の確保方法(新規借地、農業承継 など)
- 販売戦略(直販/JA出荷/ネット販売)
- 収穫・販売までの生活費と運転資金
就農に必要な資金は、以下の3つに分類して考えるのがポイントです。
| 資金の種類 | 主な内容 | 主な調達手段 |
|---|---|---|
| 初期投資資金 | 農機具、施設、農地整備など | 補助金/融資(公庫・信金など) |
| 運転資金 | 種苗・資材・人件費・販促費など | 補助金(投資資金など)/融資 |
| 生活資金 | 収穫までの生活費 | 農業次世代人材投資資金(経営開始型) |
このように分けて考えることで、どの費用にどの制度が使えるかが整理しやすくなります。
多くの支援制度では、事業計画書や営農計画書の提出が求められます。
特に「農業次世代人材投資資金(経営開始型)」を申請する場合には、市町村の認定を受けた「青年等就農計画」が必須となります。
就農計画には以下のような内容を盛り込みましょう:
- 農業を始める動機と目的
- 栽培作物と経営方針
- 設備・施設の導入計画
- 年間収支計画(売上・経費・利益)
- 支援制度の活用プラン
不慣れな方は、市町村の農政課やJA、農業委員会に相談しながら進めると安心です。
補助金・助成金は予算枠が限られていることが多く、申請時期や審査スケジュールが決まっています。
特に春〜夏に募集が集中する傾向があるため、「始めたい時期から逆算して、半年前には準備を開始する」ことが理想です。
また、制度によっては「就農前に申請が必要」なものもあるため、農作業を始めてしまってからでは遅いというケースも少なくありません。
早期の相談が成功への近道
資金調達の準備において大切なのは、「すべてを一人で抱え込まないこと」です。
新規就農支援センター、JA、地域農業委員会などには、就農希望者向けの相談窓口があり、制度選定や書類作成のサポートを受けることができます。
また、農業承継を考えている方は、FARMLINKのようなマッチングサービスを活用することで、最初から“譲り手”との話を並行して進めることが可能です。譲渡条件により、「設備無償提供」や「家賃不要」など、資金面で非常に有利なケースも多く存在します。
💡 資金調達も“戦略”のひとつ
農業起業において、資金計画は単なる準備ではなく、経営の安定性と継続力を左右する“戦略”です。
現実的な見積もりと制度の活用、そして地域の支援を味方につけることで、就農へのハードルは大きく下がります。
次章では、ここまでの内容をふまえ、費用の不安を乗り越えて就農を実現するためのまとめをお届けします。
6. まとめ|費用の不安を“情報と制度”で解決しよう
「農業を始めたいけれど、資金面が心配で踏み出せない」
そう感じている方は少なくありません。
ですが、今回ご紹介したように、新規就農には補助金・助成金・融資制度といった支援の仕組みが豊富に用意されており、それらを上手に活用すれば、資金の不安を大きく減らすことができます。
また、「すべてをゼロから準備する」だけが就農の方法ではありません。
農業承継という選択肢を取れば、農地・設備・販路などを引き継いでスタートすることができ、初期費用も時間も大幅に削減することが可能です。
🌱 FARMLINKでは、後継者を探している農家と、農業を始めたい人をマッチングすることで、
「高額な初期投資がネックで踏み出せなかった方」にとっても、現実的で効率的な就農ルートを提供しています。
就農には、確かに準備と覚悟が必要です。
けれど、「知らないから不安」だったことの多くは、情報を得て整理することで、ちゃんと解決できる問題でもあります。
自分に合った支援制度を活用し、必要な準備をし、信頼できる相談先を見つければ、農業という新しい生き方は、もっと手の届くところにあるはずです。
費用の不安を理由に夢を諦めるのではなく、正しい情報と行動で、“実現可能な計画”に変えていきましょう。
あなたの就農の一歩を、FARMLINKも全力で応援しています。