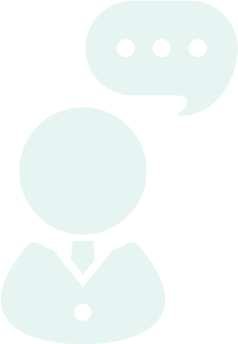1. はじめに|今、企業が農業に参入する時代へ

かつて「農業」といえば、家業や個人経営の専売特許というイメージが強くありました。しかし近年では、まったく異業種の企業が農業へと参入する動きが全国的に加速しています。食品メーカーはもちろん、IT企業、建設業、物流会社、小売業など、多彩な業種が“企業の新規事業”として農業に注目し始めているのです。
背景にあるのは、農業の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加といった社会的課題。このような課題に対し、企業が持つノウハウや資本力、販路を活かすことで解決の糸口となると期待されています。また、持続可能性(SDGs)への貢献や、CSR活動の一環としての価値も注目され、単なる事業としての意味を超えた新しい企業活動のかたちとなりつつあります。
さらに、テクノロジーの進化により、農業にITやAIを掛け合わせた「スマート農業」も現実味を帯び、異業種企業にとっても取り組みやすい土壌が整ってきました。
今、まさに「農業は企業のビジネスチャンス」であり、「社会に貢献する新たな事業フィールド」でもあるのです。本記事では、そんな企業農業の魅力や参入のステップ、成功事例までをわかりやすく解説していきます。
2. 企業が農業に参入する3つのメリット
企業が農業に参入する背景には、単なる「新規事業の開拓」にとどまらない多くのメリットが存在します。ここでは、特に注目すべき3つのメリットを紹介します。
1. CSR・SDGsとしての価値が高い
農業は環境保全・地域貢献・食料安全保障といった社会的課題に直結しています。そのため、企業が農業に取り組むことで「社会的に意義のある事業」として高く評価され、SDGsへの取り組み実績やブランディングにもつながります。とくにESG投資の対象として注目されるケースも増えています。

2. 新規事業としての広がりがある
農業は生産だけでなく、加工・販売・観光・教育などとの組み合わせによって多様なビジネス展開が可能です。たとえば、農産物を使った自社ブランド商品の開発や、直販ECサイトによるマーケティング強化など、他事業との連携によって6次産業化(1次×2次×3次産業)も実現可能です。
3. 社員育成や組織活性化に役立つ
地方での農業研修や農場運営への関与は、社員のチームビルディングやキャリア開発にもつながります。自然と向き合う農作業は、「ものづくり」や「マネジメント」の原点を見つめ直す機会にもなり、企業文化の再構築や人材育成の場としても活用されています。
3. 企業として農業を始める3つのステップ

企業が農業事業に参入するには、業界特有のルールや準備すべき項目が多数あります。参入障壁が高いと感じられがちですが、正しいステップを踏めば、無理のないスタートが可能です。ここでは、企業が農業を始める際の基本的な3ステップを、実践的な観点から詳しく解説します。
まず最初に行うべきは、「なぜ自社が農業をやるのか」という目的を明確にすることです。これは、単なるコンセプトづくりではなく、事業の持続性や方向性を左右する重要なポイントになります。
たとえば、自社のSDGsやCSR活動の一環として地域と連携した農業を行うのか、あるいは本格的な収益事業として6次産業化を目指すのか。または、自社製品とのシナジーを狙って原材料を自社栽培するのか。その目的によって、栽培する作物や選ぶ農地、必要な人材・投資額まで大きく変わってきます。
目的が定まったら、次に行うのが具体的な事業計画の立案です。収支シミュレーション、販売戦略、栽培スケジュール、必要な機材・人材、行政との調整スキームなどを含めた実行可能なプランニングが必要です。また、行政や農業委員会、金融機関、地域農協との連携も視野に入れながら、外部の専門家に事前相談することも成功への近道になります。
農業を始めるには、当然ながら「農地」が必要です。しかし日本では、農地法により、農地の取得や利用には厳格な制限が設けられています。特に企業の場合、「農地所有適格法人(旧:農業生産法人)」でなければ農地を所有・借用することはできません。
この「農地所有適格法人」には、農業を主たる事業とすること、役員の過半数が農業従事者であることなど、実現が難しい要件もあります。そのため、多くの企業では、まずは農地中間管理機構(各都道府県が設置)を通じて農地を借りるところからスタートするケースが増えています。
また、土地選定時には、気候・土壌・水利などの環境条件だけでなく、近隣住民や地域農家との関係構築のしやすさも重要です。自治体によっては企業農業を積極的に支援している地域もあり、地域選びが成功の分かれ道になることもあります。
農業は想像以上に専門性が高く、現場での判断力や経験が結果に直結します。企業が自前の人材だけで農業を始めようとすると、思った以上に手間取り、失敗するリスクも高まります。そのため、農業経験者の採用や、地域の熟練農家とのパートナーシップを早期に築くことが重要です。
さらに、近年はドローン、センサー、AI分析などを活用した「スマート農業」の導入も進んでおり、企業がもつITやDXのノウハウが活かせる場面も多くあります。効率化・省力化を前提とした運営モデルを構築すれば、農業初心者の企業でも安定した生産体制を実現しやすくなります。
あわせて、社内での意思決定フローやリスクマネジメント体制の整備も欠かせません。農業は天候や市場価格の変動リスクを抱えるため、複数年での経営計画や、事業リスクの分散設計を行うことが求められます。
このように、企業としての農業参入には、明確なビジョンと計画性、法的理解、そして現場に根差した運営体制が必要です。段階的に準備を進めることで、持続可能で社会的意義も高い農業事業をスタートさせることができるでしょう。
4. 農業法人化する?子会社として始める?法人形態の選択肢

企業として農業に参入する際、「どのような法人形態で運営するか」は、事業の安定性や農地取得の可否に直結する重要なポイントです。ここでは、主な2つの選択肢とそれぞれの特徴を紹介します。
4-1. 自社内に農業部門を設置する
既存の企業内に農業部門を新設する方法です。すでに法人格を持っている企業が行うため、手続きや資金の移動もスムーズです。CSRや福利厚生の一環として位置づけたい場合や、まずはスモールスタートで試したい企業に向いています。
ただし、自社が農地を取得・借用するには「農地所有適格法人」の要件(事業の主たる内容が農業、役員の過半数が農業従事者など)を満たす必要があります。このハードルが高い場合には、次の選択肢も検討が必要です。
4-2. 農業専用の子会社を設立する
農業を本格的な新規事業として展開したい場合には、農業専用の子会社を新たに設立する方法が適しています。事業を切り出すことで、リスクの分離や経営管理がしやすくなります。また、子会社を「農地所有適格法人」として位置づけることで、農地取得も可能になります。
この形を選ぶ企業は、以下のようなパターンが多く見られます。
- 食品関連企業が、自社ブランド野菜の生産を目的に設立
- 建設業やエネルギー業が、耕作放棄地を活用した農業ソリューション事業を展開
- 地方創生に取り組む企業が、地域密着型の農業法人を立ち上げ
4-3. 農地取得を目的としない場合の柔軟な選択肢
なお、農地を直接取得しない方法もあります。たとえば契約栽培(委託栽培)や農業法人との共同出資・パートナー契約などを通じて、自社のブランド戦略や商品開発と連動させる方法も選択肢の一つです。
このように、企業の農業参入には、目的や規模感に応じた柔軟な法人形態の選択が必要です。農地法や関連制度との兼ね合いを事前にしっかり確認しながら、最適な形を模索しましょう。
5. 企業農業を支援する制度・補助金一覧

農業に参入する企業にとって、初期投資や人材確保などのハードルは決して小さくありません。ですが、国や自治体は企業の農業参入を後押しするさまざまな支援制度を用意しています。ここでは、活用しやすい代表的な支援制度を紹介します。
5-1. 農業経営基盤強化準備金(経営開始型)
新たに農業を始める法人や個人が、一定の要件を満たすことで受け取れる準備金制度。農業に必要な設備投資や資材の購入、農地の整備などに活用可能です。
企業が新規就農者を雇用して事業を立ち上げる際にも活用できる場合があります。
5-2. 農地中間管理機構の活用
各都道府県に設置されている農地中間管理機構を通じて、農地の貸借をスムーズに行える仕組みです。農地法の制約を受けにくく、企業が農地を借りやすくなるため、初期参入の障壁を下げる役割を果たします。
5-3. 企業版ふるさと納税
企業が地域振興のための事業に寄付を行うことで、最大で寄付額の約9割が法人税等から控除される制度。農業振興や地域活性化のプロジェクトに企業として関与できるだけでなく、地元とのつながりやPR効果も期待できます。
5-4. 地域活性化起業人制度
地方自治体と連携して、都市部企業の社員を一定期間、農業や地域事業に派遣できる制度。実際に現場を経験することで事業化のヒントを得たり、地域ネットワークを構築したりする機会としても活用できます。
これらの制度をうまく組み合わせることで、企業としての農業参入をコスト・手続きの面から支援することが可能です。特に自治体によっては独自の支援策を設けている場合もあるため、地域に根差した情報収集と行政との連携が成功のカギとなります。
6. まとめ|「農業×企業」は社会課題も解決する次世代ビジネス
企業が農業に参入することは、単なる「新しい収益源の確保」にとどまりません。高齢化による担い手不足や耕作放棄地の増加といった社会課題に対して、ビジネスの力でアプローチできる手段として注目を集めています。
実際に、多くの企業が自社の強みを生かして農業に挑戦し、CSRやSDGsの観点からも高く評価される事例が増えてきました。加工・販売・観光・教育などとの掛け合わせにより、6次産業化の実現や農業DXの推進といった、新たな可能性も広がっています。
もちろん、農業特有の法制度や運営上の課題も存在しますが、制度や補助金、専門人材との連携を通じてリスクを抑えながら実行可能です。まずは小規模に始め、地域と共に成長していく姿勢が成功の近道となるでしょう。
「農業×企業」は、社会に必要とされる次世代型のビジネスモデル。
自社らしいかたちで、持続可能な未来に向けた一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。