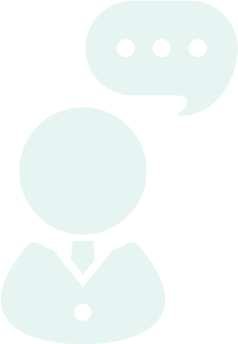1. はじめに|今、農業で“起業”を目指す人が増えている

「農業で起業」という言葉に、あなたはどんなイメージを持つでしょうか?
一昔前なら、「起業=ITや飲食、コンサル」などが定番で、農業はどちらかというと家業や継業の延長線上にあるものでした。しかし今、農業を“ゼロからのビジネス”として捉え、起業の手段として選ぶ人が着実に増えています。
背景には、地方移住や自然志向の高まり、そして何より「食」や「持続可能性」への関心が強まっていることがあります。自分の手で作物を育て、それを商品として世の中に届ける――そのプロセスはまさに“起業そのもの”。農業はもはや「家業」ではなく、価値創造のフィールドとして大きな注目を集めているのです。
とはいえ、未経験から農業ビジネスを立ち上げるには、明確な戦略と実行力が必要です。農地の確保、資金の調達、販路の設計、そして事業として成立させるための視点。これらをバランスよく備えることが、成功のカギになります。
本記事では、「農業×起業」をテーマに、未経験者でも農業ビジネスを立ち上げるためのステップや考え方、活用できる制度・サービスをわかりやすく解説します。
「農業を仕事にしたい」「自分で事業を立ち上げてみたい」――そんな思いをカタチにする第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。
2. 農業は“起業のフィールド”として本当にアリ?

「農業で起業って、本当に成り立つの?」
そう疑問に思う方もいるかもしれません。しかし結論から言えば、今の農業は、ビジネスとして大きな可能性を秘めた“起業のフィールド”です。
① 市場としての安定性とニーズの高さ
まず、農業は「食」を支える産業であり、景気に左右されにくい強みがあります。人々が生きていく限り、食べ物への需要がゼロになることはありません。特に近年は、国産・無農薬・オーガニック・地産地消といった価値に注目が集まり、「高付加価値の農産物」に対するニーズが拡大しています。
② スマート農業・6次産業化などの新潮流
農業といえば「体力勝負」「高齢化」「効率が悪い」というネガティブなイメージを持たれがちですが、今や状況は大きく変わりつつあります。ドローン、センサー、IoT、AIなどを活用したスマート農業の普及や、加工・販売まで一貫して行う“6次産業化”によって、収益性の高い農業モデルが広がっています。
これにより、従来のように大量生産・出荷に依存するだけでなく、ブランド農産物や自社商品の開発、EC販売など、多様なビジネス展開が可能になってきました。
③ 作るだけでなく「売る」「伝える」も自分の手で
農業起業の魅力は、「育てる」ことだけにとどまりません。作物を“商品”として捉え、パッケージやストーリーを設計し、自分の言葉で発信しながら直接届ける――マーケティングやブランディングの要素を存分に活かせる仕事でもあります。
特にSNSやネット通販を活用すれば、小規模生産でもファンを獲得し、収益を安定させることが可能です。「自分らしい農業」を起業という形で確立できる時代が、すでに始まっています。
農業は、これからの時代にふさわしい“起業の舞台”のひとつです。次章では、実際に農業で起業を実現するためのステップを、未経験者向けにわかりやすく解説していきます。
3. 農業起業の基本ステップ【未経験でも実現可能】

「農業で起業したい」と思っても、何から始めればよいのかわからない――。
特に未経験の方にとっては、農地の確保や資金調達、知識の習得など、不安要素が多く感じられるかもしれません。ですが、順を追って着実に準備をすれば、農業での起業は決して夢物語ではありません。
ここでは、未経験者でも実現可能な農業起業の基本ステップを5つに分けて、わかりやすく解説していきます。
農業は単に作物を育てる仕事ではなく、「どんな価値を誰に届けるか」を自ら考え、形にしていく事業です。
そのため、まず最初に必要なのは「なぜ農業をやりたいのか?」という自身のビジョンを明確にすること。
例えば、「子育て世代に安心安全な野菜を届けたい」「地域の耕作放棄地を再生して、新しい雇用を生み出したい」「果樹を育てて、自社ブランドの商品を展開したい」など、農業を通じてどんな社会的・経済的価値を提供したいのかを言語化することが、起業の土台になります。
このビジョンが明確であればあるほど、後の地域選びや作物選定、販路開拓の軸がぶれず、ブランディングや発信の説得力も増します。
ビジョンが定まったら、次は「どこで、何を育てるか」を具体的に考えるフェーズです。
このステップは、事業の実現可能性を大きく左右する重要な判断ポイントになります。
農業は自然との相性が不可欠です。作物の栽培適地は、気温・降水量・土壌・水資源などの条件によって大きく異なります。 例えばトマトのように日照と排水のよい環境が求められる作物もあれば、米のように水田が必要な作物もあります。
また、地域によって支援制度の充実度や販売ルートの整備状況、地元の農家コミュニティとの距離感なども大きく異なります。現地見学や体験就農を通じて、その土地の“空気感”まで肌で感じることが大切です。
さらに、作物の選定は「自分が作りたいもの」だけでなく、「消費者が求めているもの」「売れるもの」という視点も欠かせません。生産と販売のバランスを意識した選定が、事業としての安定性を高めます。
農業起業において、最も大きな壁の一つが「農地」と「設備」の確保です。
農地を探すにも、農地法の制約や地域の慣習が関係してくるため、都市部での不動産探しとは異なり、すぐに借りたり買ったりできるわけではありません。
また、ハウス・農機・倉庫といった生産設備の整備にも大きな費用と手間がかかります。ゼロからスタートする場合、思った以上の時間と資金が必要になるのが現実です。
そんな中で、今注目されているのが「農業承継」という選択肢です。
これは、高齢化や後継者不在で農業の継続が難しくなっている農家から、農地や機械、販路、技術などを引き継いで起業する方法です。
🌱 FARMLINKは、農業承継に特化したマッチングサービス。
全国の「託したい農家」と「始めたい人」をつなぎ、農地・設備・経営資源ごと引き継ぐという形での農業起業をサポートしています。
ゼロからではなく、すでに整った環境でスタートできるため、コストや時間を大きく節約できます。
特に、すぐに実践を始めたい人や、地域との関係性に不安がある人にとっては、農業承継は最短で信頼と資源を得られる現実的なルートと言えるでしょう。
農業は作って終わりではなく、売れて初めて“ビジネス”として成り立ちます。
どこで誰にどう売るのか――この販路設計は、事業の利益構造を左右する極めて重要なパートです。
販売方法には、以下のような多様な選択肢があります。
- 地元の直売所や道の駅への出荷
- 飲食店・加工業者との契約販売
- 自社サイトやECモールでのネット販売
- SNSを活用したファンマーケティング型直販
- ふるさと納税への出品による認知獲得と収益化
また、作物の特性や収穫時期に合わせて販路を組み合わせ、複数の収入源を持つことがリスク分散にもつながります。
さらに、単に売るだけでなく、加工・保存・定期便サービスなどの形で「農業+α」の付加価値を作ることも、安定した収益を生む鍵となります。
農業起業にかかる初期費用は、栽培規模や設備内容によって異なりますが、農地整備・機材購入・住居改修・販路構築など、ある程度まとまった資金が必要です。
そこで活用したいのが、国や自治体が用意している就農支援制度です。
- 農業次世代人材投資資金(最大150万円/年)
- 農業近代化資金(長期・低金利の設備資金)
- 各自治体の移住・起業支援金制度
- FARMLINKの承継農家による設備無償譲渡や支援付き承継パターン
これらの制度を組み合わせて活用すれば、自己資金が少ない場合でも実現可能性は十分にあります。
また、事業計画を作る段階でこれらの制度条件を把握しておくと、スムーズな資金調達が可能になります。
以上が、未経験から農業で起業を実現するための基本ステップです。
「やってみたい」だけで突き進むのではなく、ビジョンを描き、戦略を練り、資源を効率的に使うことが成功への鍵です。次章では、農業起業を軌道に乗せるための「3つの成功ポイント」をさらに深掘りしていきます。
4. 農業起業を成功させるための3つのポイント

ポイント1|“マーケット視点”を忘れない
農業というと、「自分が育てたい作物を育てる」ことに注目しがちですが、成功する農業起業家は“売れる作物”を見極める力に長けています。
つまり、農業も他のビジネスと同じく「需要があるか」「競合が多すぎないか」「どう差別化できるか」といったマーケティング的な視点が不可欠なのです。
たとえば、地元で人気の直売所があるエリアでは、その直売所で売れ筋の野菜を把握するところから始められます。
都市部の飲食店に卸すなら、流通・保存性の高い品種が有利ですし、ネット販売に力を入れたいなら、見た目やストーリー性のある作物が相性が良いでしょう。
成功している農業起業家は、「栽培のしやすさ」だけでなく、「買い手が求めているものは何か?」という視点を常に持ち、“売るための農業”を設計しています。
ポイント2|利益を出せる仕組みを最初から考える
農業は、設備投資や人件費、肥料・資材費など、意外とコストがかかる産業です。
「作ってからどうにかする」ではなく、起業前の段階から“どうすれば利益が出るか”を逆算して設計しておくことが極めて重要です。
収支モデルを考える際には、以下のような要素を整理しましょう。
- 1年あたりに栽培・収穫できる面積と数量は?
- どの販路を使って、どの価格で販売できるか?
- 1回の売上に対して、かかる経費はいくらか?
- 経費を引いた後に残る利益(手取り)はどれくらいか?
農業は自然を相手にする以上、常に不確実性が伴います。だからこそ、“利益が出る構造”を最初から組み込んでおくことで、経営の安定性が大きく変わります。
また、「加工品販売」「定期便サービス」「EC販売」「イベント出店」などのサブモデルを組み合わせることで、季節ごとの収入変動を和らげる工夫も必要です。
ポイント3|“人とのつながり”を味方につける
農業は一見孤独な仕事に見えるかもしれませんが、本当に成功している人ほど、地域・農家仲間・専門家・顧客などとのつながりを大切にしています。
とくに未経験者にとっては、「聞ける相手がいる」だけで、乗り越えられる課題が何倍にも増えるものです。
技術的なこと、経営のこと、制度のこと……一人で抱え込まずに、信頼できる人に相談できる関係性を早い段階で築いておくと、いざというときに心強い支えになります。
その意味でも、農業承継という形で地域に入ることは大きなメリットです。
すでにその土地で農業を営んできた方から、ノウハウや販路だけでなく、「地域で農業を続けるための知恵」や「人との関係性」ごと引き継げるからです。
FARMLINKのような農業承継支援サービスを通じて始めた方の中には、「農地や設備以上に、人のつながりを引き継げたことが大きかった」と語る方も多くいます。
つながりは、農業経営の安定だけでなく、あなたの“続ける力”にもなってくれるでしょう。
これら3つのポイントを意識しながら計画を立てることで、農業というフィールドでも、しっかりと「稼げる事業」を育てていくことができます。
5. まとめ|農業は「起業の選択肢」として、もっと注目されるべき
起業といえば、これまで多くの人がITや飲食業、物販などを真っ先に思い浮かべてきました。けれど今、「農業」という分野が新たなビジネスのフロンティアとして静かに注目を集めています。
食の安全・地方創生・サステナビリティ・一次産業の再構築――こうした社会課題にダイレクトに関わりながら、自らの手で価値を生み出せるのが農業という仕事の本質です。
そしてそれは、単なる生産にとどまらず、ブランディング・販売・商品開発・体験価値の提供まで含めた、まさに“総合ビジネス”としての農業でもあります。
もちろん、未経験で始めるには不安もつきものです。
農地の確保、資金の準備、販売戦略の設計……乗り越えるべきハードルは少なくありません。
だからこそ重要なのは、「ゼロからすべてを築く」以外のルートを知ること。
その選択肢のひとつが、すでに実績と資源を持つ農業経営を引き継ぐ“農業承継”という方法です。
🌱 FARMLINKは、農業を始めたい人と、農業を託したい人をつなぐマッチングサービスです。
農地・機械・販路・技術、さらには地域とのつながりまで――
ゼロからの起業では得られない「スタートダッシュの土台」を提供することが、私たちの役割です。
起業とは、自分の信じる価値を形にすること。
そして農業とは、その価値を“食”というかたちで、誰かの暮らしに届けること。
あなたの起業のアイデアが、農業というフィールドで実を結ぶ未来は、決して遠いものではありません。
新しい農業のカタチを、一緒に育てていきませんか?